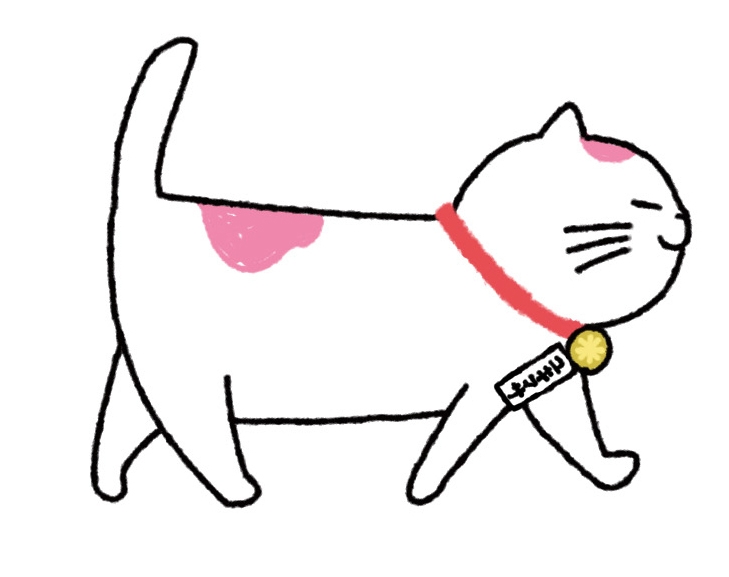1.共同相続と遺産分割
ある方が亡くなり、法定相続人が複数いる場合、共同して財産(債務も含む)を相続します。共同相続人は、遺言で禁じられた場合を除き、相続開始後いつでも、その協議で遺産の分割をすることができます。
有効な遺産分割協議となるためには、相続人全員の合意が必要です。一人でも反対者がいる場合は、有効な協議分割ができないため、さらに協議を継続したり、合意見込みがなければ、遺産分割の調停や審判の検討をすることになります。
2.遺産分割の当事者
相続放棄の意思を家庭裁判所へ申し出た人は、最初から相続人とならなかったものとみなされるので、遺産分割協議の当事者となりません。
また、例えば夫が亡くなり、相続人である妻が妊娠中で胎児がいた場合、この胎児も被相続人(父親)の相続人となります。この場合は死産の可能性もあることから、出産を待って出生した子のための特別代理人を選任してから遺産分割協議をします。
さらに、判断能力のない相続人や行方不明の相続人がいる場合など、その所定の手当てをして遺産分割協議をする必要があります。
3.遺産分割の内容
遺産分割の方法には現物分割や換価分割、代償分割などいくつかの方法があります。例えば自営業者などの営業用財産などがある場合、事業承継者が営業用財産のほとんどを相続し、代わりに代償金を他の相続人へ支払うケースなどがあります。
また、いわゆる法定相続分は協議における一定の指針を示すとともに、裁判規範としての役割があります。しかし、当事者の合意内容は、必ずしもこの法定相続分と一致する必要はありません。
4.遺産分割の効果
遺産分割の効果は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じます。よって、遺産分割は協議成立の時に分割されるのではなく、相続開始の時にさかのぼって分割されたことになります。
5.遺産分割協議書
遺産分割の合意ができたときは、その合意内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。遺産の中に不動産や預貯金が含まれる場合、その登記手続きや預貯金の解約、名義書き換えにおいて、この遺産分割協議書が遺産分割について合意が成立した証拠として重要な役割を果たします。