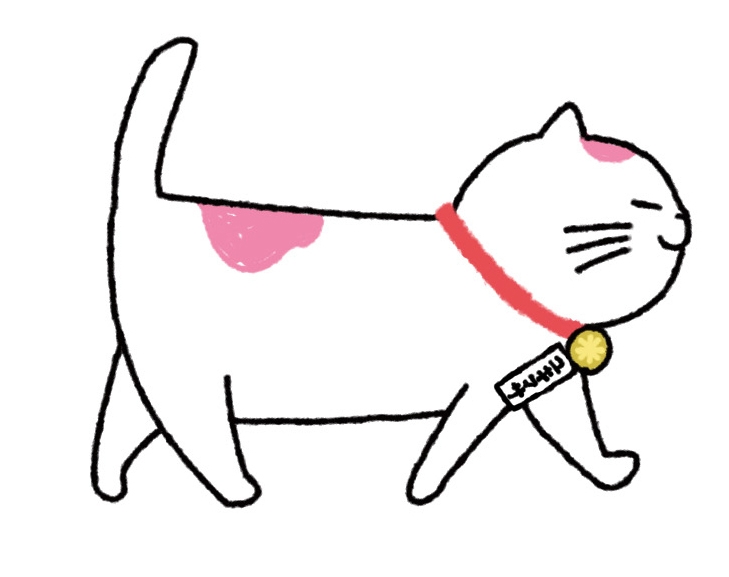◆事例1 自分の判断能力が低下したら・・・
5年前に夫を亡くし、息子は遠方にいます。70歳で一人暮らしとなり、少し物忘れもあります。もしも自分が認知症などになったときのことが心配です。今後、息子には迷惑をかけたくないので、自宅を処分し施設に入居しようかと考えています。どのようにすれば良いでしょうか?
◆事例2 持病のために思うように動けなくて・・・
65歳で一人暮らしです。今後、持病が悪化して寝たきりになったり、認知症になったときのことが心配です。今は判断能力に問題はないですが、持病で足腰が弱り思うように動けません。財産管理などを誰かに依頼することはできますか?
◆事例3 子どもがいないので自分の死後のことが気になります。
73歳で子どもはおらず、夫も亡くしたため一人暮らしです。兄もすでに亡くなりその子どもたち(甥と姪)も遠方に住んでいます。夫が残してくれた預貯金があり、年金もあるので生活に支障はありませんが、私が死んだ場合のことが不安です。私の葬儀や埋葬、病院の支払いやお寺のことなど、どのようにしておけばよいでしょうか。
◆事例4 日常生活の支援をしてもらいたいのだが・・・
71歳で一人暮らしです。一人暮らしが不安なので、施設に入居することも検討しています。私が認知症になってしまうと入居の契約など不安なため、信頼できる親戚に後見人になってもらう予定です。後見人の代理行為には、日常生活の補助は含まれていないと聞きました。買い物や通院の同行、また墓参りの補助など日常生活の支援をしてもらうと安心なのですが、どのようにすればよいでしょうか。